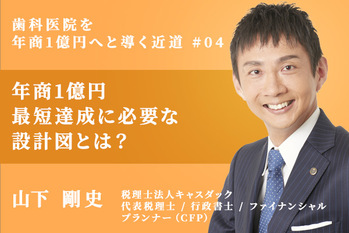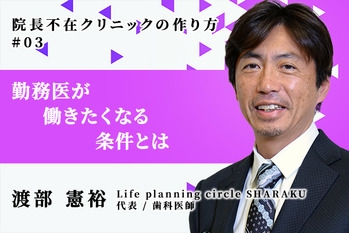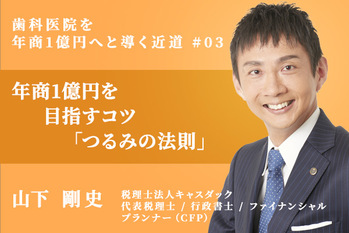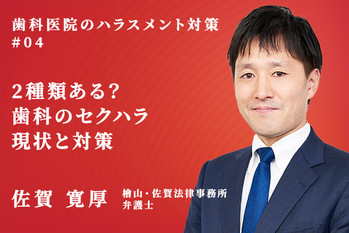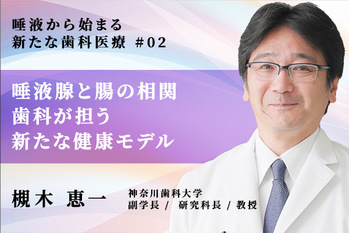歯科医院が全身の健康の入り口を担う存在となることで、診療の幅も大きく広がります。
私たちの研究によって得られた知見が新たな健康モデル、新たな産業の創出に寄与することができれば幸いです。
今回は「唾液ケアの普及が歯科医院に新機軸をもたらす」と題して、日本唾液ケア研究会発足までの経緯や活動についてご紹介します。
日本唾液ケア研究会発足までの経緯

唾液の作用を量と質の2つの面から捉える「唾液力」
私たちが「唾液腺健康医学」を創設してから早15年が経過しました。
その少し前の2002年くらいから、ドライマウスがブームとなり、唾液の重要性は社会全体で広く知られるようになりましたが、歯学部での研究は、唾液腺局所での現象を追求することがほとんどでした。
そこで私たちは、唾液の量の意義だけでなく、質の重要性まで周知されるよう、この15年の間でさまざまな研究に取り組んできたのです。
この取り組みの結果、唾液・唾液腺と全身との連関性を科学的に明らかにし、唾液の作用を量と質の2つの面から捉える「唾液力」を提案することで、唾液腺健康医学の必要性への意識も徐々に高まりつつあります。
ただし、その認知度はまだまだ十分ではありません。おそらく多くの先生方も「唾液力」という造語を今回の連載で初めて目にしたことかと思います。
唾液力をあげる取り組み「唾液ケア」
そんな中、新型コロナウイルスの蔓延は唾液が持つ力を予期せぬ形で全世界へ広めることになりました。まさに、不幸中の幸いです。
前回は、唾液IgA抗体が未知のウイルスに対して備えていたこと、新型コロナウイルスに対するワクチン接種後に唾液からIgG中和抗体が認められたことなどをお伝えしました。
その後、パンデミックによって健康志向が高まった今、唾液力にさらなる注目が集まることかと思います。
そして今、強く求められているのが「唾液力をどう上げるか」という方法論です。
幸いなことに、唾液力は比較的簡単にセルフケアによる向上が望めます。
私たちは、この唾液の量と質を上げることを唾液力と表現し、唾液力を上げる取り組みを「唾液ケア」と定義づけました。
実は、唾液ケアは単に唾液を良くすることに留まらず、全身の健康や口腔機能低下を防ぐ手段にもなったのです。
従来の口腔ケアでは、唾液の「量」を増やすことに腐心しており、そこが異なる点です。
唾液量の増加だけでも口腔及び全身に、良い影響がもたらされることは間違いありませんが、「質」にも働きかける必要があります。
そうした新たな医療の構築、新しい産業の創出も視野に入れた上で、私たちは令和3年4月に「日本唾液ケア研究会」を発足しました。
日本唾液ケア研究会を発足
唾液腺健康医学という分野を設立した私たちがこれまでの活動を組織化し、唾液の健康効果を普及させるために発足したのが日本唾液ケア研究会です。
唾液ケアを推進し、国民の健康に寄与するための社会貢献をしていく組織となっています。 唾液は歯科の十八番であり、歯科医療を超えた存在に、どう育てていくかを共有する場でもあります。
先生方にもお力添えをいただけたら幸いです。
終わりに

日本唾液ケア研究会では、11月28日を「いいつばのひ=いい唾液の日」として、日本記 念日協会に申請し、2021年8月6日に認められました。
各歯科医師会、スタディグループ、企業など唾液に関心のある方すべてが、それぞれの立場で、いい唾液の日を記念していただき盛り上げていただけたらと存じます。
また、11月は11月8日の「いい歯の日」もあり、11月28日の「いい唾液の日」の2つと併せて、口腔という臓器の健康を国民にアピールできます。
11月を口腔から全身の健康月間にしたいとも思っています。
最後に唾液ケアの普及が歯科医院にイノベーションを起こし、新産業を創出することを願っております。歯科医師、歯科衛生士が唾液をみることで、歯科医院の可能性は無限に広がっていくことでしょう。
※本連載記事は2021年11月28日の講演内容を元に再構成したものです。
【おすすめセミナー】
・【無料】たった4ヶ月で歯科衛生士276名の応募獲得! 歯科衛生士・歯科助手採用セミナー
・【無料】矯正治療が得意な先生に贈る マウスピース矯正集患セミナー