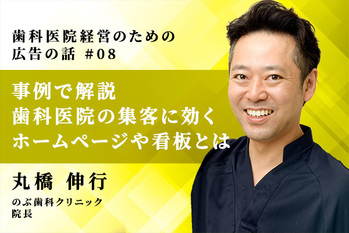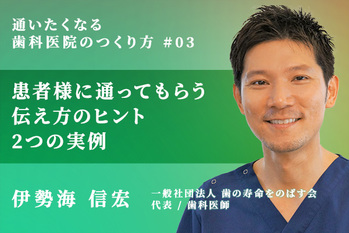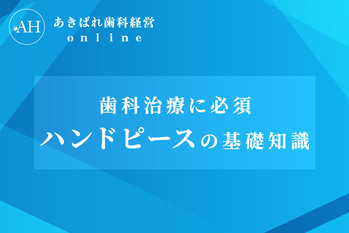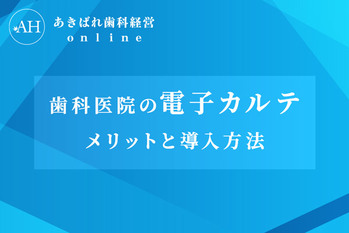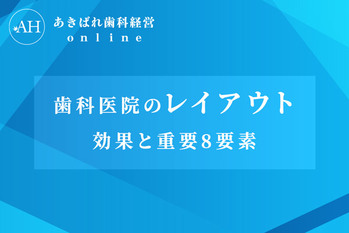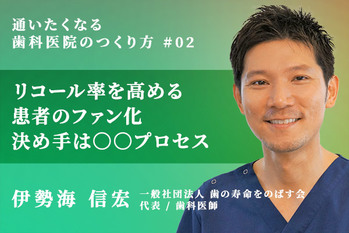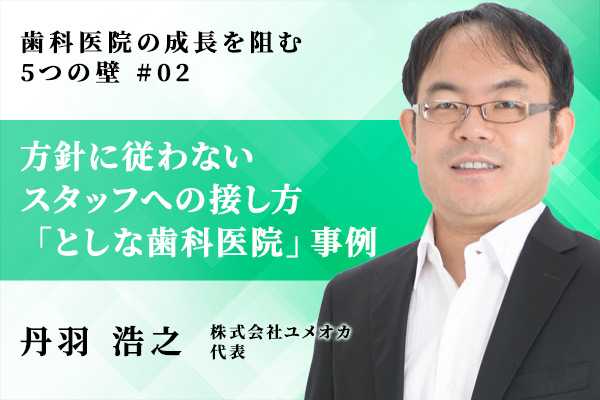先日(2022年11月27日(日))に、無事に第1回日本唾液ケア研究会学術集会が開催することができました。
私自身、唾液研究を 15 年ほど続け、こういった会の立ち上げを準備をしてきましたので、 多くの方にご参加いただけて、大変嬉しく思います。
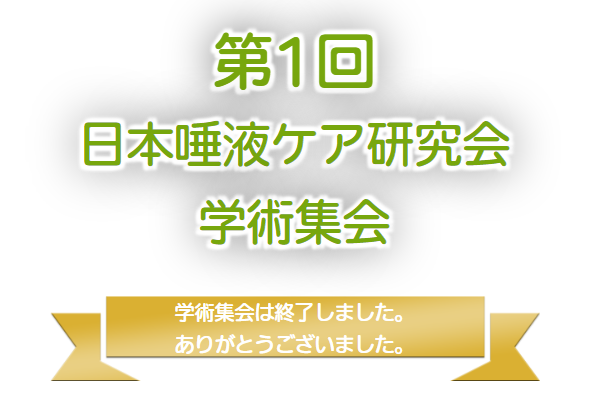
■唾液ケア研究会とは 唾液ケア研究会は、「特定非営利活動法人 日本唾液ケア研究会」として2022年4月21日に神奈川県より NPO 法人に認可されました。
「NPO 法人として設立した」という意味は大変大きく、私たちには「唾液意義を広める活動を通して社会貢献をし たい」という考えがあります。
私も長く唾液の研究をしていますが、「唾液の重要性がなかなか理解されていない」というのは大きな課題です。
理解を広めるにはしっかりと研究をして学術的に発表をしていくことが重要であるにも関わらず、今まではその場 がなかったのです。
それが第 1 回日本唾液ケア研究会学術集会となります。
本日オンラインも含めて大変多くの方々が、この活動に興味を持ってご参加くださいました。
唾液の効果に興味がある方がこれだけいらっしゃることに大変心強く思いますので、ぜひ皆様と共に「唾液の持つ 効用を広めて社会貢献に繋げる」活動を進めていきたと考えています。
■唾液の「質」の重要性と質の変化
あらためて唾液についてお話をしますと、唾液の「量」と「質」がそれぞれ大切で、この研究を 15 年続けてまいりま した。
質というのは唾液の成分のことです。単に唾液の分泌量を増やすのではなく、質を上げていくことも重要で す。
唾液の成分というのも、時間と共に変化しています。
もともと農耕民族だった日本人は、「お米を多く食べていたためにアミラーゼが増えた」と言われています。
しかし 欧米の食生活が入ってきたことや食文化の変化などにより、少しずつ唾液の質も変化・進化しているのです。
■唾液の質を上げるために
唾液は口腔内の健康維持のためにとても大切なのですが、その唾液の質を上げるために重要なことは、口腔内の環境をよくすること、「唾液ケア」です。
「口腔ケア」という言葉は昔からありますが、「唾液の機能性」を考えるという意味から「唾液ケア」という言葉を作り ました。
歯科医師はどうしても歯そのものばかりに注意がいきますが、その周りの環境因子=唾液もとても重要なカウンタ ーパートナーなのです。
しかしその重要性はあまり認知されておらず、ドライマウスなどのように「なくなって初めて ありがたみがわかる」状況です。
ここを私たちは改善し、しっかりと重要性を伝えていきたいと考えています。
■唾液ケアは全身の健康へもつながる

唾液ケアに重要なのは口腔の健康を整えることですが、これは現在の「口の中の清掃」が主流の口腔ケアだけで少し足りないように思います。